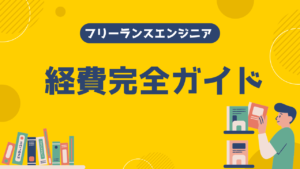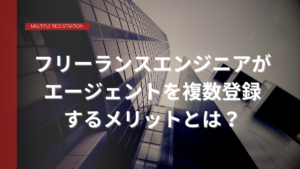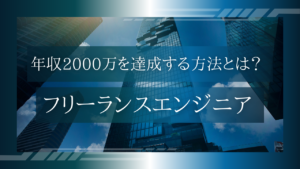クラウドとは?基本からメリットまでをわかりやすく解説

近年、「クラウド」や「デジタル・トランスフォーメーション(以下、DX)」という言葉をビジネスの場でよく耳にするようになりました。DXとは、デジタル技術を活用してビジネスにおける変革を目指す取り組みです。クラウドは、導入スピードの速さや従量課金によるコスト管理のしやすさから、DXを始める第一歩として最適です。
本記事では、DX実現の手段として注目されているクラウドの特徴やサービスモデルの違い、クラウド導入のメリットについて、わかりやすく解説します。
クラウドとは
Webアプリケーションやシステムなどが自社環境になく、インターネット上にあるクラウド事業者のサービスで行うことを「クラウド(クラウドコンピューティング)」と呼びます。利用者は、クラウドサービスの中身を知らなくても、サービスとして利用できます。
企業がクラウドを利用する場合、コンピュータやソフトウェアを自社で保有するのではなく、サービスとして利用するモデルになります。
クラウドの定義
NIST(アメリカ国立標準技術研究所)が、「NIST によるクラウドコンピューティングの定義」のガイドラインとして公開しています。詳しくは、クラウドコンピューティングの定義が参考になるでしょう。
クラウドコンピューティングは、共用の構成可能なコンピューティングリソース(ネットワーク、サーバー、ストレージ、アプリケーション、サービス)の集積に、どこからでも、簡便に、必要に応じて、ネットワーク経由でアクセスすることを可能とするモデルであり、最小限の利用手続きまたはサービスプロバイダとのやりとりで速やかに割当てられ提供されるものである。
引用:NIST によるクラウドコンピューティングの定義
クラウドの5つの特徴とは
「NISTによるクラウドコンピューティングの定義」に基づいて、クラウドの特徴を解説します。

1.オンデマンド・セルフサービス
利用者がクラウド事業者と直接やりとりせず、クラウドサービスの管理画面から自由に設定変更を行えることを意味します。
例えば、Amazon Web Servicesではインターネット経由でアクセスできる「AWS マネジメントコンソール」がこれに該当します。
2.幅広いネットワークアクセス
さまざまなプラットフォーム(パソコン、スマートフォンなど)からインターネットを通してクラウドサービスにアクセスできることを指します。
3.リソースの共用
クラウドサービスのコンピューティングリソースを、複数のユーザーが共有するかたちで利用できることを指す。サーバを仮想的に分割し、各ユーザーが専用のコンピューティングリソースを割り当てられ、あたかも専用のリソースを利用しているかのように使用できる仕組みです。このような仕組みをマルチテナントと呼びます。
4.スピーディな拡張性
サーバを必要に応じて必要な分だけ「スケールアウト/スケールイン」や「スケールアップ/スケールダウン」といったように伸縮自在に拡張が行えることを指します。
例えば、サーバの負荷状況に応じて、サーバの台数を増やすことをスケールアウト、逆にサーバの台数を減らすことをスケールイン。
一方、サーバの処理能力を向上させることをスケールアップ、逆に処理能力を減少させることをスケールダウンと呼びます。このように、伸縮自在にサーバの台数やスペックを必要に応じて柔軟に調整ができます。
5.サービスが計測可能であること
クラウドサービスは、サービスの利用状況が常に計測されていることを意味します。そのサービスを使った分だけ支払う従量課金となっています。
クラウドのサービスモデル
クラウドを選択する際、求められる要件に合ったサービスモデルを選択することが大切です。例えば、Webアプリケーションをオンプレミスからクラウドへ移行する場合は、導入するサーバに細かいカスタマイズが必要であればIaaSを選択。一方、カスタマイズが不要で、Webアプリケーションの動作環境/実行環境のみ必要であればPaaSが適しています。
このように、適切なサービスモデルを選ぶためには、それぞれの特徴を理解しておくことが重要です。
IaaS
IaaS(Infrastructure as a Service)とは、OSから上位レイヤーを提供するサービスです。
利用者はハードウェアを保有することなく、仮想サーバを必要なときに必要な分だけ作成することができ、その仮想サーバを自由にスケールアップやスケールダウンすることが可能。また、ミドルウェアやアプリケーションを自由にインストールすることも可能です。
代表的なサービスは、Amazon Web Services、Microsoft Azure、Google Cloudなどが挙げられます。
PaaS
PaaS(Platform as a Service)とは、アプリケーションの開発環境や実行環境を提供するサービスです。
インフラ部分はクラウド事業者が管理するため、利用者はインフラ運用を行う必要がなく、アプリケーション開発に注力ができ、運用コストも抑えることが可能。ただし、サーバやミドルウェアのチューニングを行うことができないです。代表的なサービスやソフトウェアは、kintoneやCloud Foundryなどが挙げられます。
SaaS
SaaS(Software as a Service)とは、主に業務で使用するソフトウェアをインターネット経由で提供するサービスです。
SaaSのサービス契約後、すぐにサービスの利用が開始できます。ソフトウェアの更新は、クラウド事業者が行うため、常にバグ修正やセキュリティ対策が適用され最新の状態で利用可能。代表的なサービスは、GmailやOffice365などが挙げられます。
各サービスモデルの責任分界点
クラウドサービスの契約や利用にあたって、クラウド事業者と利用者の責任範囲を事前に把握しておくことが重要です。サービスモデルごとに、クラウド事業者と利用者の責任範囲が異なります。クラウド事業者の責任範囲が広いほど、利用者の運用コストが軽減できます。下図では、それぞれのサービスモデルによる責任範囲を示しています。
クラウドの利用モデル
クラウドの利用モデルは、「パブリッククラウド」「プライベートクラウド」「コミュニティクラウド」「ハイブリッドクラウド」の4つのモデルがあります。
企業では、パブリッククラウドやハイブリッドクラウドがよく利用されています。パブリッククラウドは、Webサイト構築やアプリケーション開発などで利用されています。一方、ハイブリッドクラウドは、オンプレミスとパブリッククラウドを組み合わせてBCP(事業継続計画)対策などで利用されています。
パブリッククラウド:
クラウドのインフラストラクチャは広く一般の自由な利用に向けて提供される。その所有、管理、および運用は、企業組織、学術機関、または政府機関、もしくはそれらの組み合わせにより行われ、存在場所としてはそのクラウドプロバイダの施設内となる。
プライベートクラウド:
クラウドのインフラストラクチャは、複数の利用者(例:事業組織)から成る単一の組織の専用使用のために提供される。その所有、管理、および運用は、その組織、第三者、もしくはそれらの組み合わせにより行われ、存在場所としてはその組織の施設内または外部となる。
コミュニティクラウド:
クラウドのインフラストラクチャは共通の関心事(例えば任務、セキュリティの必要、ポリシー、法令順守に関わる考慮事項)を持つ、複数の組織からなる成る特定の利用者の共同体の専用使用のために提供される。その所有、管理、および運用は、共同体内の1つまたは複数の組織、第三者、もしくはそれらの組み合わせにより行われ、存在場所としてはその組織の施設内または外部となる。
ハイブリッドクラウド:
クラウドのインフラストラクチャは二つ以上の異なるクラウドインフラストラクチャ(プライベート、コミュニティまたはパブリック)の組み合わせである。各クラウドは独立の存在であるが、標準化された、あるいは固有の技術で結合され、データとアプリケーションの移動可能性を実現している(例えばクラウド間のロードバランスのためのクラウドバースト 4)。
4 (訳注)burst とは爆発とかはじけるという意味であり、「クラウドバースト」はクラウド間をまたがる移動や連携を意味する概念として使われるケースが多い。定義の確定した用語ではないと考えられる。
参考:http://sites.google.com/site/cloudcomputingwiki/Home/cloud-co
引用:NIST によるクラウドコンピューティングの定義
クラウドのメリット
オンプレミスと比較したクラウドのメリットは以下の通りです。
コスト面
オンプレミスの場合、サーバのサイジングには利用時のピークを想定してスペックを決める必要がありました。そのため、ピーク時以外ではサーバのリソースに余剰が生じていました。
一方、クラウドでは最低必要限のスペックでスモールスタートすることができ、利用状況に応じて柔軟にスケールアップやスケールダウンが可能です。ピーク時以外のリソースの無駄を最小限に抑え、コスト効率を高めることができます。
拡張性
オンプレミスの場合、サーバの増設には高度な技術が必要で、ハードウェアの調達に時間がかかることや物理的な設置場所などの問題で柔軟な対応が困難でした。
一方、クラウドではWeb画面から簡単にサーバの増設をすることができ、ハードウェアの調達や物理的な設置場所の考慮は不要です。増設したサーバで予期せぬ問題が発生した場合はWeb画面からサーバを削除ができるため、状況に応じて柔軟に対応できます。
可用性
オンプレミス環境での災害対策として、データベースサーバのデータバックアップを磁気テープなどで取得し、物理的に離れた拠点などへ保管する方法が一般的でした。
一方、クラウドでは複数のデータセンタにデータベースサーバを分散配置(マルチAZ構成)ができます。これにより、1つのデータセンタが被災しても、他のデータセンタにあるサーバへ自動的に切り替わりサービスを継続することが可能。
まとめ
クラウドの特徴やサービスモデルの違い、クラウドのメリットについて解説してきました。求められる要件に応じて適切なクラウドサービスを選択することで、本来の業務に注力できる環境が整います。また、DXの第一歩としてクラウドサービスを導入することで、変化の激しいビジネス環境にも柔軟に対応が可能になります。これにより、企業としての競争力の向上やイノベーションを加速することが期待できます。 イーランサーではフリーランスエンジニアのサポート、企業様へのご支援をさせて頂いております。是非お気軽にご相談下さい。